試験前日
会場下見

試験当日にドタバタしないよう、起床から会場入りまで事前に予行演習しておくことに。
- 朝5時に起床して
- 軽く体幹トレーニングを行い、シャワーを浴びて
- コンビニに行って朝食を購入し、部屋に帰って朝食を摂り
- 7時15分ごろホテルを出て
- さっぽろ駅から地下鉄南北線で北18条駅まで向かい
- 駅から西方面へ歩く
このような行程を実際に踏んで計画にミスがないかどうか一応確認。ホテルから試験会場まではおおよそ30分程度。二次試験開始は08:40。その1時間前には試験教室に入っていたかった。明日はもう10分程度早くホテルを出発しなければならない。外で行動してみて感じたのは、そこまで寒いわけではないという点。屋外に出ている時間はごく僅か。屋外仕様の服装だったら屋内では暑く感じられるかも。ヒートテックじゃなくてエアリズム等の薄い下着の方が快適。ただ、エアリズムを着て行って会場で寒さを感じた時には地獄。ヒートテックなら暑くても脱げる。試験本番は予定通り、ヒートテックを身にまとってテストへ挑むことに。
時計はまだ朝8時にもなっていない。このままホテルに帰っても手持ち無沙汰になる。少し北大構内を散策してみようか。銀世界の札幌キャンパスは何度歩いてみても気持ちが良い。メインストリートを南進し、北図書館の交差点を右折。北部食堂の南を通ってラクロスコート、そして陸上競技場へ。赤ふんどしで有名な恵迪寮の前に到着。YouTubeで寮生が寮の窓から雪山に向けて飛び降りる動画を見、世の中にはこんなにクレイジーな奴らが存在するのかと衝撃を受けたのを思い出した。もしかしたら次の瞬間、窓が開いて寮生がダイブするかもしれない。衝撃の光景を生で目撃すべく5分ほど寮を眺めていたものの、雪山に飛び込む野生の寮生を見られず、諦めて地下鉄駅に引き返した。
まだ10時にもなっていない。暇だ。もう何もやることがない。飯を食って勉強するか。コンビニで食事を調達してホテルに戻ってむしゃむしゃと頬張る。
テキストの総復習
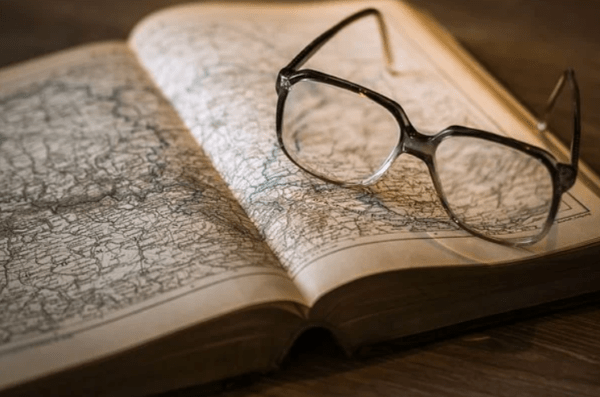
前述の通り、浪人時代の目標は総合理系主席合格。落ちる恐怖と戦いながら合格最低点越えを狙って勉強していた昨年の京大受験と違い、浪人時代は当落線上の勝負ではないため割と気負わず勉強できた。センター試験では国語で失敗して85%。センターリサーチの結果は総合理系80位。80位から1位を狙うのに守りもへったくれもない。自分は挑戦者。一点にこだわり、攻めて攻めて攻めまくる姿勢で首位を勝ち取らなければならない。主席合格を達成すべく、試験当日へ脳の調子を合わせにかかった。受験全科目の総復習。取り出したい知識を脳からすぐ引き出せるよう、知識を加工・整理していった。
4~5時間かけて勉強を終了。ひと息ついて夕食を摂り、浪人の一年を回想した。
回想

ベッドへ横になるや否や、京大に落ちたあの日の悔しさがふつふつと鮮明に蘇ってきた。中3から京大だけを目指して4年間勉強してきた。A判定だった。それでも落ちた。不合格になったショックは相当なものだった。落ちてから一か月ほどは悲しくてシャーペンを持てなかったほど。4月後半に”6点差で落ちた”と知り、悔しくて再起できた。
あと6点で逃した合格、次こそは何が何でも超えて見せる。闘争心に火が付いた。5月から8月末までは入試直前期並みの勉強。その甲斐があり、夏の京大オープン模試では農学部A判定&冊子掲載。マーク模試との合計点は昨年度の合格ラインを余裕で上回る結果。
ただ、私のエネルギーはここで尽きた。自分のキャパを上回るほど追い込んだせいで体が耐えられなくなってしまった。このまま京大を目指していては試験を受けに行くことすらままならない。このままの学力を維持して合格できる大学を目指すしかない。悔しいけど、二浪だけは無理だから。いくつか候補があった中で北海道大学を選択。キャンパスが素敵で通っていて癒されそう。総合理系もある。入学前に進路を決めずに済む総合理系は魅力的に映った。
大変失礼な物言いだが、正直、北大に合格するのは余裕だと思っていた。河合塾の全統記述模試では総合理系で常に一桁順位。入試問題は難しく感じられない。気の緩み以外で落ちる要素が見当たらなかった。北大へ単に合格するだけでは面白くない。そこで首席合格をターゲットに据えた。10月末の北大オープン模試では総合理系3位。受験者全体で40位。一位との差は10~20点ほど。主席合格は射程範囲内。トップ合格だけを目指して勉強してきた。
明日は自分の全てを出し尽くす。出し惜しみなどせず、最初から最後まで突っ走る。もし疲れて動けなくなっても構わない。北大病院のお医者さんの手に掛かればすぐ直してもらえるだろう。これで安心して全力を出せる。死んでもいい。死力を尽くして1位を取りに行く。決戦を前にして戦意が昂じてきた。それを宥め、深呼吸して落ち着いて一日を終えた。
















