こんにちは。札幌と筑波で電池材料研究をしている北大化学系大学院生のかめ (M2)です。B4、M1、M2と年次を経るにつれ資料作成スキルがどんどん高まり、ゼミで炎上する気配がどんどんなくなっていっています。
研究室配属当初は如何にしてゼミの用意をすればいいか分かりませんでした。回数を重ねるにつれ要領を掴み、手際よくパパっと準備・対策できるようになったのです。
この記事では、雑誌会を平和に乗り越えられるようになった5ステップを皆さんに披露したいと思います。
- ゼミ発表を間近に控えた学部生や大学院生
- その子たちを指導する立場にある上級生の皆さん
こうした方々に是非読んで頂ければ幸いです。
 かめ
かめそれでは早速始めましょう!
雑誌会(論文紹介)を乗り切る5ステップ
雑誌会を無事に乗り越えるために提案するのは以下の5ステップ⇩
- 論文を選ぶステップ
- 論文を深く理解するステップ
- プレゼン用スライドを作るステップ
- 発表練習のステップ
- 当日に向けて体調を整えるステップ
各段階について、以下で一つずつ解説します。
【4~3週間前】紹介用論文を慎重に選ぶ
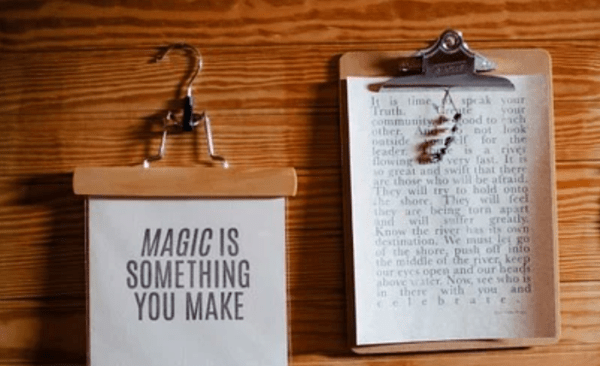
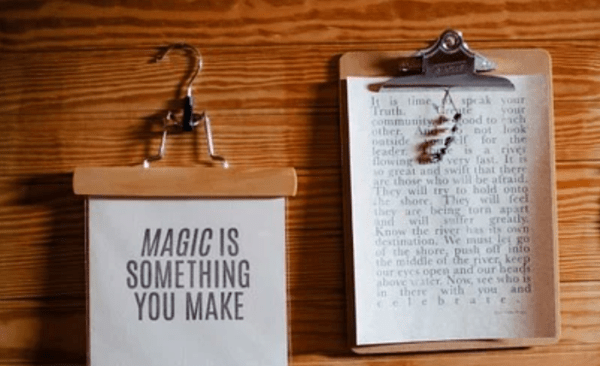
第一段階は論文を選ぶステップ。炎上しにくく発表しやすいそうな論文を慎重に選んでください。論文紹介では論文選びか重要。論旨が不明瞭だったり難しすぎてよく分からなかったりするる論文は炎上を招きやすい傾向が。論文を選ぶ際に気を付けるべきは以下の4つのポイント⇩
- 議論のレベルが理解できる範疇か
- 論旨が自然か/不自然ではないか
- 筆者の主張に違和感がないか
- 論文紹介するのに適切なボリュームであるか
論文選びを軽視しないように。炎上回避への道は論文を選ぶ段階から始まっています。
【3~2週間前】論文を自力で読み進めて完全な理解を目指す
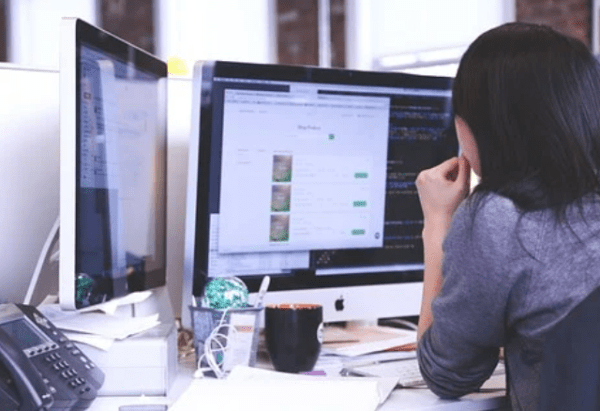
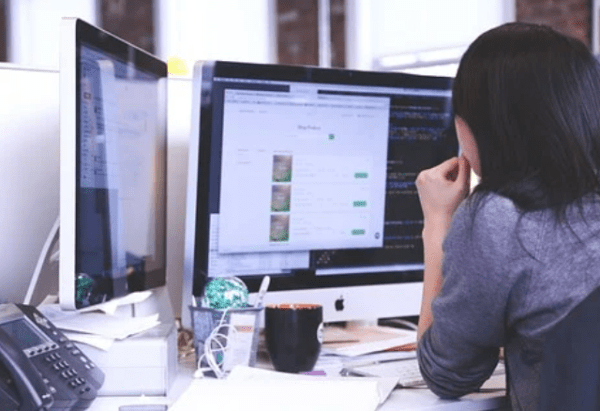
選んだ論文を読む第二ステップへ。論文中の隅から隅まで熟読し、何を言っているか把握しましょう。一行たりとも読み落としてはダメ。イントロ、実験方法、実験結果、結論と全て読み込みましょう。論文内容に関連し、装置の測定原理や実験材料の選定理由をも調べておくと安心。素人質問にも対応できる万全の体制を整えられます。
なお、論文を読む際、英語に抵抗のない方は原文のままで読みましょう。英語にやや抵抗感のある方はChatGPTやDeepLを用いて日本語に訳してから読んで下さい。英語を読むのが目的ではありません。英語で書かれた論文の”中身”を理解するのが目的。最終的には英語で読めるようになって欲しい。最初は日本語訳を読んで内容の理解に努めるだけでも大丈夫。
【2週間前】雑誌会用スライドを作り始める。作成中に生じた疑問点を各個撃破


第三ステップは発表スライドを作る段階。自分が苦悶して理解した内容をスライドへ詰め込んで下さい。作成の際、その論文を一度も読んだことのない人にでも伝わる表現を心掛けて貰いたい。なるべく想像の付きやすい表現を心掛けたり、専門用語を使う際には解説を入れたりして親切なプレゼンが出来るように。資料から聴衆への思いやりを感じるスライドは炎上を招きにくい傾向が。頑張って作った感が滲み出ているからでしょう。
プレゼン資料を作っている間に、これまで気付かなかった疑問点が沸き上がってくるはず。今まで理解していたつもりだったあれやこれやが「そういえばどういう意味だったっけ…」と理解の至らなさに気付くはず。作成中に明らかになった疑問点を各個撃破して下さい。一人理解すれば論文の理解度が一段ずつ着実に上がっていくでしょう。プレゼン作成の過程で湧き上がってきた疑問点は、かなりの確率で本番で問われがち。あっさりスルーしたら終わり。詰みます。炎上待ったなし。”多分こんなマニアックな質問など誰もしないだろう♪”と高をくくらないで下さい。下準備は少々やり過ぎなぐらいがちょうどいいんです。
【1週間前】発表練習を実施。聞いている人にちゃんと伝わるかどうか自問してみる


意外と見過ごされているのがこの第四ステップ【発表練習】。本番に弱いタイプならもちろん、本番に強いタイプを自称する方でもしっかりと練習しておいて下さい。プレゼンはなるべくよどみなくスラスラと喋れた方が得。プレゼンターがつっかえひっかえしている発表は聞きづらく、聴衆をイライラさせてしまいます。毎日最低一度は最初から最後まで通して練習しましょう。予行演習で明らかになった課題点や不明瞭な点は本番までに残さず解決しておくように。
【前夜〜当日】よく寝て体力を養い、頭をフル回転させ命懸けでゴールを目指す


発表前日はよく寝て英気を養いましょう。徹夜はダメ、絶対にダメです。徹夜で準備するぐらいならもっと早くから準備しておくべき。徹夜明けは脳のパフォーマンスが下がって頭が回りません。最低でも6時間は寝て臨みましょう。あわよくばぐっすり8時間寝たいもの。英気に溢れた頭でもって思考回路をフル回転させ、無事の終幕を目指しましょう。
最後に
雑誌会での論文紹介は、私が提唱する5ステップを意識すればきっと乗り越えられるはずです。
全ては論文選びから始まります。自分の理解できるレベルの、論旨の明確な論文を選ぶことで、後の準備がずっと楽になるでしょう。その上で、論文を徹底的に読み込む。内容についてどのように問われても答えられるよう理解を深めていく。ここでの努力は、必ず質疑応答で活きてきます。
スライド作成では思いがけない発見がありました。資料を作る過程で新たな疑問点が次々と浮かび、それを解決していくうちに理解がさらに深まっていったのです。また、発表練習の重要性も身をもって実感しました。徹底的に練習を行うことで本番での余裕が生まれます。
そして最後に、十分な睡眠を取って臨むべし。これは意外と軽視されがちですが、実は成功への鍵を握っています。



















コメント