こんにちは!札幌と筑波で電池材料研究をしている北大化学系大学院生かめ (M2)です。研究室配属当時はゼミで全く発現できずに虚無感を覚えていたものの、修士課程進学以降、質問のコツを会得したおかげで積極的に発言できるように。
この記事では、全然質問できなかった私がポンポン質問できるようになった方法を実体験からお伝えします。質問したくても質問が思いつかない学生さんにピッタリな内容なので、ぜひ最後までご覧いただければ幸いです。
 かめ
かめそれでは早速始めましょう!
そもそも、質問をする意味とは?


質問できるようになった方法をお伝えする前に、そもそも質問にはどのような意味があるのか一緒に考えていきたいと思います。
研究は『問い』を設定する所からスタートします。世間で”当たり前”とされていることを疑ってみて、疑問の種を起点とし、未だ人類の誰も聴いた事のない知見を得に行く行為が研究。研究のスタート地点は必ず自分で設定します。誰かに決めてもらうわけじゃない。スタートラインの白線は自分で引くのです。たとえ卒論だろうが修論だろうが同じこと。この一年間で取り組む課題を設定するのは自分自身。
ゼミで質問をする目的は、研究遂行にあたって最も重要となる『問いを打ち立てる力』を養うこと。分からないことを分からないと気付いたり、頭の中で漠然と生じた疑問を言語化する能力を身につけたりするために行うのです。質問すればするだけ益々”問う力”が高まっていくはず。研究センスがおのずと磨かれていき、最終的には独力でテーマを打ち立てられるだけの研究構想力をも培えるという仕組み。皆さんはゼミ中、先生から「○○さんは質問ないかな?」と言われて嫌な気持ちになったことはありませんか?私はあります。あるんだけれども、よく考えてみれば先生から『問いを打ち立てる訓練に参加してみない?』というお誘いだったワケです。そう気付くまでに3年かかりました。
ゼミで質問できるようになった4つのマインドセット
とはいっても、この記事を読んで下さっている方の中には『そんな簡単に質問が思いつかないからこの記事に辿り着いたんじゃないですか…!!』とお考えになった人がいらっしゃるはず。そこで以下では、私がゼミで質問魔になるにあたって習得した4つのマインドセットについてお話しします。
一時の恥などかき捨てろ!


もしかすると、質問が苦手な貴方は質問するのがなんとなく恥ずかしいから質問をためらっていらっしゃいませんか?恥ずかしがり屋の貴方に伝えたいのは、そんな恥じらいなんて捨てて下さいというメッセージ。たとえゼミで変な質問をしても周りの人は明日になったら忘れていますよ。こういうものって自分しか覚えていません。笑われてもいいじゃないですか、どうせ明日になったら忘れられているのだから。一時の恥などかき捨てましょう。恥ずかしくない。大丈夫。どんな素人質問でもプレゼンターは答えてくれます。
分からない事を分かるために専門分野をある程度勉強する
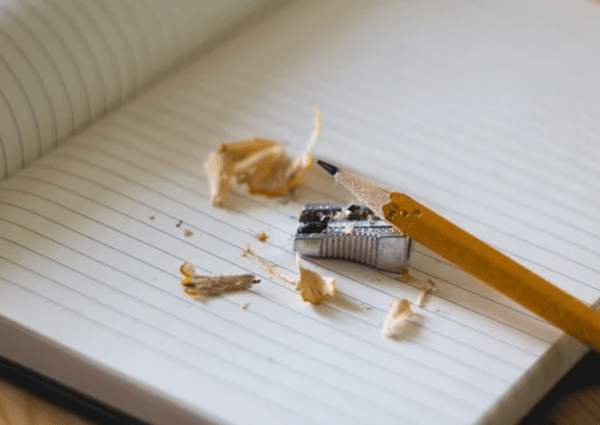
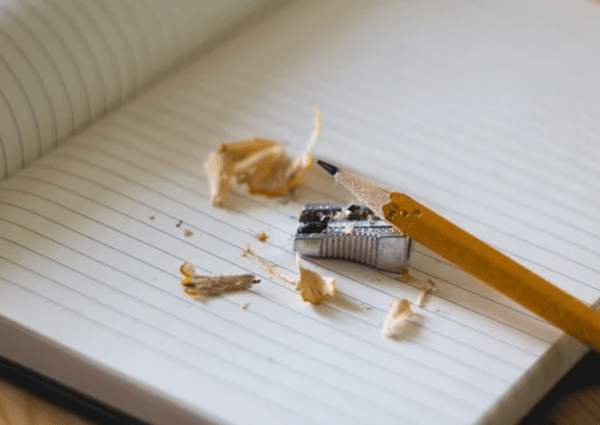
次に、先ほどのケースとはうって変わり、”何が分からないか”も分からない場合の方策を伝授します。
何が分からないかを言語化するには、その分野に関してある程度の知識が必要に。専門分野に関して全くの素人では議論が行われていてもサッパリついて行けません。私だって専門の電気化学以外の議論は分からないでしょう。数学科に放り込まれたら発狂してしまう可能性も笑。質問力を高めるためには最低限の背景知識が不可欠。まずは図解本や基本的な本を読み込む所から始めて下さい。専門用語に関しては、ゼミをしばらく聞き流していれば分かってきます。スピードラーニングと同じ。言葉が耳に馴染んでくれば大丈夫。すぐについて行けるようになりますよ。
意図的に好奇心を解放する


大学受験生時代、我々最短距離で正解にたどり着く訓練ばかり繰り返し行っていましたね。余計な回り道をしてはダメ。目的地までグネグネと蛇行して向かっていたらタイムアップになり問題を解き切られません。情報処理ばかり巧くなっちゃった。幼少期に持っていたはずの「なんで?」「どうして?」という純粋な好奇心が錆びついた状態に。もしもゼミで積極的に質問をしようと思えば、胸にしまわれた好奇心を発掘し、意図的にさらけ出してやる必要があります。好奇心の表面を覆う錆を取り去って活性化してあげなくてはなりません。好奇心を表に出すためには、発表中に考え続けるのが大事。”どうしてそのような考察が成り立つの?”とか”本当にそうかな?”と思索し続けるのが効果的。
自分事で聴く&何かを質問する前提で発表を聴く


発表を聴く時、あなたはそれをさも他人事であるかのように聴講してはいませんか?もしも自分事でゼミに出なければ、おそらく何年経っても質問力は上がらないままでしょう。ゼミを少しでもプラスな時間にしたければ、他人事ではなく自分事で聴く必要があるのです。もしも自分がこのスライドを使って発表するとしたら、発表前にスライドのどの部分を調べて確認しておきたいだろうか…と。発表を自分事として真剣に聞いていると、やがて『何か質問する前提で聴く』能動的な姿勢が出来上がるでしょう。こうすれば質問がまるで雨後のタケノコのように次々と生まれてきます。
最後に
私が質問できるようになった4つのマインドセットに関してはコレで以上となります。
おさらいすると、
- 一時の恥などかき捨てろ!
- 何が分からないかを分かるため、図解や教科書で最低限の知識を仕入れておこう
- 意図的に好奇心を解放しよう
- 自分事で聴く&質問する前提で話を聴こう
これらが本記事の要点となります。
当記事が質問でお悩みの全国のゼミ生に役立てば幸いです。


















コメント