こんにちは!札幌と筑波で電池材料研究をしている北大化学系大学院生かめ (M2)です。M1のクリスマスイブ、博士進学希望者を支援する大学独自のフェローシップに内定しました。博士進学をしようか/しまいか決めかねていた私の背中を押してくれたのです。この内定に勇気付けられて正式に博士進学を決意しました。
この記事では、フェローシップに関するアレコレをQ&A形式にて解説します。北大生は勿論のこと、全国のフェローシップ受給希望者へ有益な情報を提供できれば幸いです。
 かめ
かめそれでは早速始めましょう!
正式名称は?
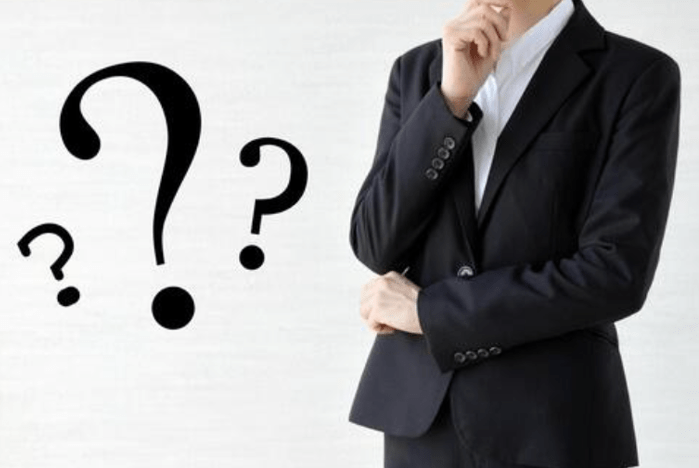
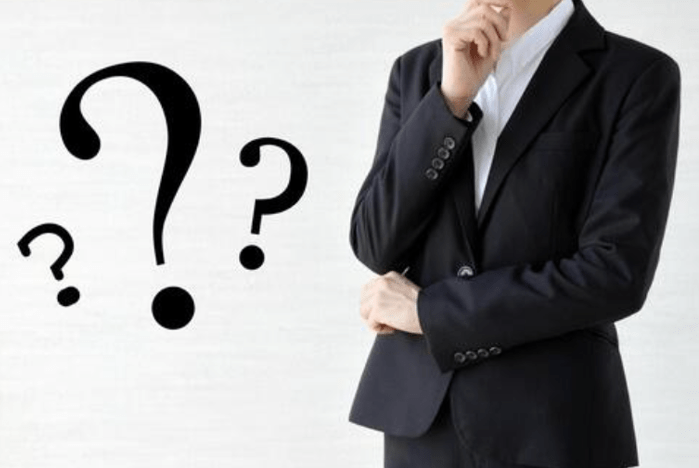
私が内定したフェローシップの正式名称は北海道大学アンビシャス博士人材フェローシップ(情報・AI)。2024年、名前が変えられ『北海道大学EXEX博士人材フェローシップ』にパワーアップ。もはや何が何だかサッパリ分かりませんね笑。スーパーヒーロー戦隊の必殺技として出てきてもおかしくないぐらい。あっ、別に名前を馬鹿にしている訳じゃありませんよ。”カッコいい”って言いたいんです。スーパーヒーローなんてみんな大好きですからね。
私が内定を頂いたフェローシップの末尾には『情報・AI』と付いています。コレを見ると文系の方や機械系の方から「何だ。自分は関係ないのか…」と落胆の声が聞こえてきそう。大丈夫、関係あります。皆さんの研究と情報・AI分野との間にほんの少しでも関連があればOK。文系の方の場合、言語に関する知見が将来、大規模言語モデル (LLM)の大幅改良に使われるかもしれません。機械工学の知見だってロボット本体を作るのに不可欠。このように、たとえ如何なる領域の研究でも別の研究領域との関連はあるのです。皆さんは”情報”や”AI”という単語にひるまず、積極的に申請してみて下さい♪
支援内容はどんな感じ?


フェローシップの支援内容は以下の通り⇩
- 月15万円の研究奨励金 [*2024年度より月額18万円にアップ!]
- 年40万円の研究費
- 博士在学中のインターンシップ
- 博士取得後のキャリアパス支援
学振DC制度よりかは見劣りするものの、博士課程で研究するのに必要な最低限の支援は得られそうな感じ。東京や神奈川、大阪など物価の高い地域で暮らす方はちょっと大変かも。指導教員におねだりしてお小遣いをもらって下さい。ちなみに北大のフェローシップは2024年度の場合、出張費が無限に支給されるそうです。研究費40万円の枠にはみ出る分の出張費も支給されるそう。国際学会へ行き放題ですよ。留学にも行けるかもしれません。
申請当時の研究実績はどのぐらい?


私が本フェローシップに申請したM1の11月末での研究実績は以下の通り⇩
- 論文2報:筆頭 1報, 3rd 1報
- 学会5回:国内 4回 (うち全国2回), 国際 1回
フェローシップの申請にあたたって研究業績がどれぐらい大事かは正直、あまりよく分かりません。ただ、研究実績欄はスカスカよりも何か書けた方が良いに違いないでしょう。何も書かれていない欄があったら見栄えが悪くて残念なのです。他の応募者との業績勝負になった時には確実に負けますし。今度フェローシップへ申し込む方は申請前になるべく多くの研究業績を集めておいて下さい。フェローシップのために集めた業績は学振DC申請時にも役に立つでしょう。
応募倍率は?


私の専攻ではちょうど一倍でした。3人の枠に対して3人が応募し、誰も落ちることなく内定が決まった形。他の専攻でも似たような感じだそう。応募者より採用枠数の方が多い状況が続いています。私の専攻の一つ上の代なんて博士進学者数がゼロ名でしたから。選考倍率はなんと、ゼロ倍。余った枠の分のお金を我々にくれたらいいのにと思いました。
学振DCとどちらが厚遇なの?
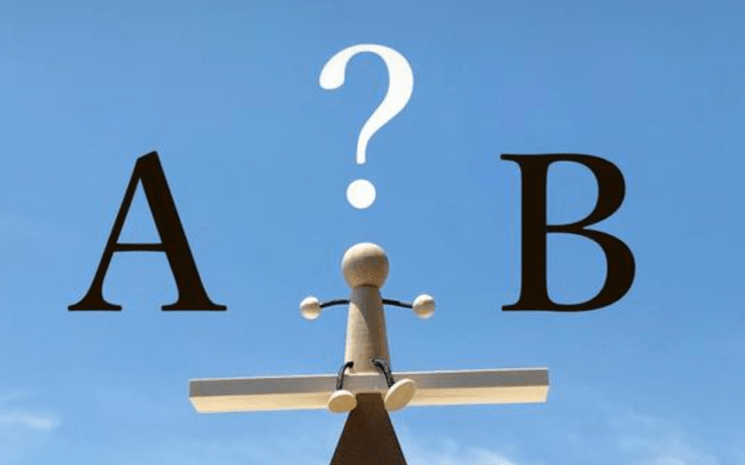
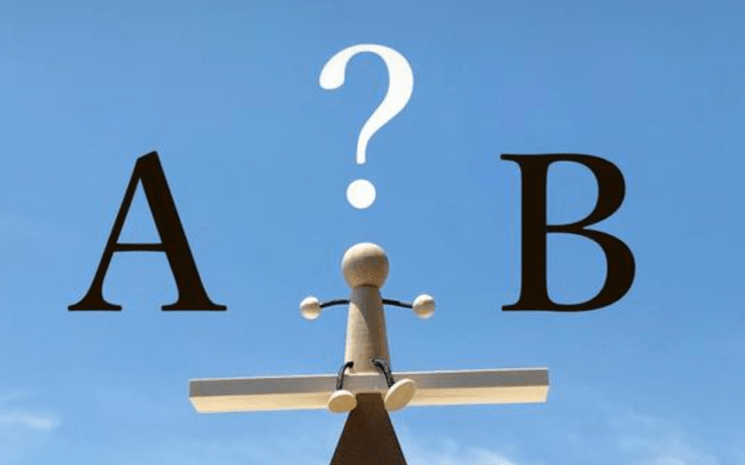
学振とフェローシップとを比較すると、金銭的に厚遇なのは間違いなく学振の方。
- 学振DC:給与月額20万円+研究費年額100万円以上 = 年額340万円以上
- フェローシップ:給与月額15万円+研究費年額40万円 = 年額220万円
このように、一年では120万円以上、3年間では360万円以上の差がついてしまうのです。私の場合、研究費は年間140万円貰っています。フェローシップを受給した場合より3年で480万円もの圧倒的大差が。
詳細な比較は以下の記事をご覧ください。


フェローシップだけで生きて行けそう?


本フェローシップはJASSO第一種奨学金との併給が可能。ただし、JASSO奨学金の返済免除対象にはならないそう。つまり、100%返さなくても構わないお金は月額15万円のみ。北大が位置する札幌市北区の場合、奨学金無しでもフェローシップだけでどうにか食いつないで行けそうです。家賃が月5.5万円。水道光熱費が月1万円。食費が月に3万円。書籍代と保険料、その他雑費で月3万円を計上。出費は合計で12.5万円。15万円の中に納まっています。
最後に
クリスマスイブに内定をもらった北大独自のフェローシップについては以上。この記事が北大生や他大学の学生に役立つことを願って記事を締めくくります。



















コメント